取材リポート
メンバー医師による
40年目の健康診断
新潟県・三条中央ライオンズクラブ
#人道支援

三条中央ライオンズクラブ(岩月正行会長/74人)は11月10日、三条市内及び周辺市町の知的障がい者らが生活する施設「いからしの里」で、無料健康診断を行った。いからしの里が開設された2年後の1982年に第1回の健康診断が行われてから、今回が40回目という節目の活動となった。
開設直後のいからしの里には、嘱託医による診察が年に2度あったのだが、内科と精神科だけで、歯科や耳鼻咽喉(いんこう)科などは診てもらえないという問題を抱えていた。当時、三条中央ライオンズクラブには82人の会員がいて、市内でも有名な医院の医師が4人在籍。しかも、内科、外科、耳鼻咽喉科、歯科と専門分野が異なっていた。クラブでは、その貴重な人材を奉仕事業に生かし、メンバーの医師たちによる施設への訪問健診をスタートさせた。

具体的にどういう経緯で始まったのか、今となっては定かではないが、いからしの里に1回目の健診を取り上げた新聞記事(『越後ジャーナル』1982年10月16日)の切り抜きが残っている。記事では、「日頃からの職員の指導による規律ある団体生活のせいか、各医師の言うことを聞き、静かに診察を受けていた。中には医者嫌いの利用者もおり、医師が苦労する場面も」と診察の様子を伝え、内科を担当したメンバー医師は「栄養がいい。食事がしっかりしているのでしょう。高血圧の人がいない。園内の健康管理がしっかりしている」と園の日頃の取り組みを評価。当時の園長は、「医療専門家の協力が得られてとてもうれしい。施設の充実だけでは本当の福祉とは言えない。園内の医療体制がしっかりしてこそ、利用者の幸せはある」と話している。
以後、年に1度の健診は途切れることなく続き、いからしの里の医療体制の一つとして組み込まれて、今日に至った。健診分野の構成は開始当時と変わらないが、担当する医師メンバーは既に代替わりしている。現在はライオンズ・メンバーがいない眼科と耳鼻咽喉科は活動に賛同した非メンバーの医師が担当。診察の項目や作業が多岐にわたる歯科でも、メンバーの他に、非メンバーの歯科医と歯科衛生士の協力を得ている。

この日は、ライオンズ・メンバー5人を含む医師8人が施設を訪れ、午前に眼科、午後からは内科、耳鼻咽喉科、歯科の健診を実施。入所者50人と通所者9人の健康状態をチェックした。
20年以上、利用者を診ているメンバーの歯科医、羽生好太さんは、治療率が上がり、口腔(こうくう)ケアの意識が高まっている印象だと話す。
「とんでもないケースがない、というのが何よりだと思っています。この健診がどれだけ寄与しているか分かりませんが、自分から口を開いてここが痛い、あそこが痛いとなかなか言えない人が対象なので、年に1度私たちがこうして診ていれば、悪い状態のまま放置されることはほぼなくなります。それが良い結果につながっているのだと思います」
羽生さんが話すように、知的障がいを持つ人は自分の症状を伝えることが不得手ため、医師や職員が気付かなければ病気が見逃されてしまうことがある。日常生活において知的障がい者が誤飲でのどを詰まらせる事故も少なくないそうで、これを危惧したクラブの健診メンバーの一人、内科の鎌田健一さんは6年前、指に挟んで血中酸素濃度を計る機器を自前で用意して園へ寄付。酸素濃度を計れば、喉が詰まっているかいないかが分かるという。また、耳鼻咽喉科では同じ患者を1年に1度でも継続して診ていれば、どういう傾向にあるか分かってくることもあるそうだ。

健康診断の結果は園に伝えられ、園の看護師や栄養士が、利用者一人ずつに立てている個別支援計画と照らし合わせて見直しを図り、安全に暮らせるように配慮。現在、40年前からこの健康診断を受けている園生が14人もいる。
いからしの里が何よりも助かっていると話すのが、施設内で健診が行われるという点だ。町の病院へ行くことを怖がる利用者が多く、例えば歯科医院では医師の前で口を開けようとしないそうだ。その点、ライオンズの健診は普段生活している場所に医師が来てくれるので、安心感もあるのかスムーズに進む。これは大きな利点だ。

健診後は、いからしの里所属の看護師や栄養士ら職員と、医師らが意見交換をする場が設けられる。この日は内科の医師から、「40年前から血圧が高い人がほとんどいないというのは、園の健康管理がしっかりしているということ。すばらしい」という報告があった。一方、園の職員からは「誤嚥(ごえん)性肺炎の恐れがあると診断された利用者がいる。普段の生活でどういう点に気を付ければよいのか」との質問が出され、医師からアドバイスを受けていた。
三条中央ライオンズクラブでこの取り組みを担当する社会福祉委員会の山田貴之委員長は、「複数の診療科の医師が外に出向いて一緒に健康診断を行うというのは、開始当時としては画期的なことだったのではないかと、改めて感じている。クラブの特色を生かして、必要としている人に貢献出来ていることを誇りに思う」と話している。
2023.01更新(取材・動画/砂山幹博 写真/関根則夫)

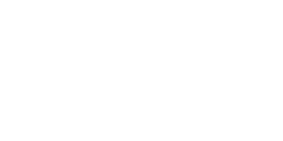 ライオン誌日本語版ウェブマガジン
ライオン誌日本語版ウェブマガジン








