取材リポート
春の始まりを告げる事業
SLのシート外し
北海道・岩内ライオンズクラブ
#人道支援

1872年、東京の新橋から神奈川の横浜の間で日本で初めて鉄道が開通した。10月14日(旧暦では9月12日)に明治天皇の乗るお召し列車が走り、翌日から正式に営業が始まった。しかし実はその3年前から、北海道では「鉄道」が走っていた。その鉄道の名は茅沼炭鉱鉄軌道。茅沼炭鉱と積み出し港となる茅沼港の間、約2.8kmを結んでいた。鉄道と言っても、レールの幅は約105cm。木のレールを鉄板で補強したもので、走るのはトロッコ。上りを牛や馬、人が引き、下りは走らせるという、一般的な鉄道のイメージからは遠いものだ。しかし、この鉄軌道を「日本初の鉄道」とする説もある。何せ、建設が始まったのは江戸時代。戊辰戦争で中断した後、明治政府が建設を進めた。
この鉄軌道で使用されていたレールの一部が北海道の岩内町郷土館に残っている。茅沼港は大型船が接岸出来るだけの大きさがなく、1931年に選炭場から岩内港まで約10kmの索道(ロープウェーのようなもの)が作られ、運ばれた石炭は岩内港を通じて各地で利用された。
陸路で言えば、岩内は1905年に岩内馬車鉄道が開通。現在の函館本線である北海道鉄道と接続していた。その後、12年に馬車鉄道から列車の走る鉄道「岩内軽便線」へと姿を変えた。22年には岩内線へと改称し、49年から国鉄に移管された。茅沼炭鉱の石炭や、岩内で盛んだったニシン漁のニシンが運ばれるなど広く利用されたが、炭鉱の閉鎖、ニシンの不漁が続くなど徐々に利用者が減少。85年に廃線となった。現在は旧岩内駅があった場所にバスターミナルが出来ており、今も岩内の交通の要となっている。
73年まで蒸気機関車が走っていた岩内線。74年に岩内町へ国鉄から蒸気機関車D51が無償貸与され、岩内運動公園に設置された。岩内運動公園は弓道場、野球場、テニスコート、陸上競技場などがあり、本格的なスポーツも楽しめる。SLの運転席は開放されていて中に入ることが出来る。SLのある広場には遊具があり、幼稚園や保育所の遠足などでも利用されている。

岩内ライオンズクラブ(菅原哲也会長/46人)は、この蒸気機関車の保全を担当している。岩内町の冬は風が強く、放っておくと日本海から吹き付ける風によって塩害が起きてしまう。そこで86年から岩内町役場の人たちで作るボランティア団体の岩内町技師会と協力し、冬の囲いとその取り外しを行ってきた。94年にはクラブから塩害防止の専用シートを寄贈。以来そのシートを11月に掛け、4月に外す活動を続けている。2014年にはところどころ剥げてしまっていたSLの塗装をし直す事業も実施した。
4月13日は冬期の潮風からSLを守ってくれたシート外しの作業日だった。朝からクラブと岩内町技師会のメンバーが広場に集まっていた。SLからシートが外れてしまわないように双方をつないでいたひもを、切っていく。SLに上り、シートを外していく作業は危険もあるので声を掛け合うことを忘れない。例会などでも発言が活発で団結が固いという菅原会長の言葉通り、メンバー同士、楽しくコミュニケーションを取りながら手際よく作業を進めていく。毎年のことだから慣れたものだ。
緑色のシートの下から黒く光るSLが姿を現した。これから11月までの7カ月間、やってくる子どもたちを存分に楽しませることだろう。

シート外しが終われば、運動公園の周辺清掃を行う。折れた木々を拾い、子どもたちがけがなどをしないようにするのだ。各自がゴミ袋を持ち、運動公園の方々へと散って行った。
しかしまだメンバーの仕事は終わりではない。今度は場所を移動し、町の南部に広がる円山周辺の道路でゴミ拾いをする。SLシート外しの日は毎年、作業後にこの清掃活動を実施することが恒例となっている。冬の間に溜まってしまったゴミが雪が溶けて姿を現すからだ。

清掃を始めると、驚くほど大量のゴミが捨てられていることが分かる。空き缶やペットボトルのポイ捨てだけではなく、明らかに捨てにきたと分かるようなゴミもある。「何で捨てちゃうのかねぇ」と言いながら、ゴミを拾う。ここでも和気あいあいとした雰囲気で作業を進めていく。ゴミ拾いにかかる時間は2時間近く。土手の下、藪の中にも入ってゴミを外へ出す。最終的にトラックの荷台いっぱいになるほどのゴミが集まっていた。

それが終われば95年に旧岩内駅前の岩内マリンパーク内に寄贈した文字盤付き時計塔のワックスがけと整備を行う。春のシート外しの日は1日、奉仕活動に従事する日だ。メンバーは疲れた顔も見せずに、それぞれの作業を行っていた。
岩内運動公園に遊びに来た人々は久しぶりに姿を見せたSLに目を留め、中をのぞいたり写真を撮ったりしていた。岩内に春が来たことを、黒く厳かにたたずむSLが教えてくれる。
2019.05更新(取材・動画/井原一樹 写真/関根則夫)

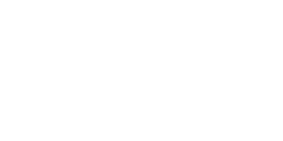 ライオン誌日本語版ウェブマガジン
ライオン誌日本語版ウェブマガジン








